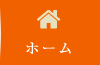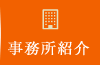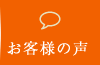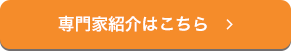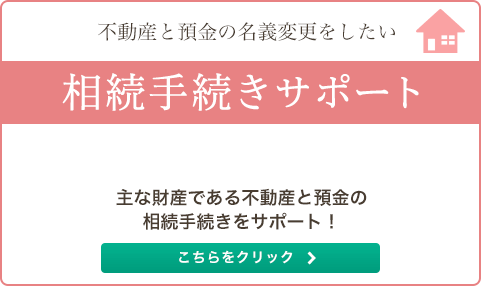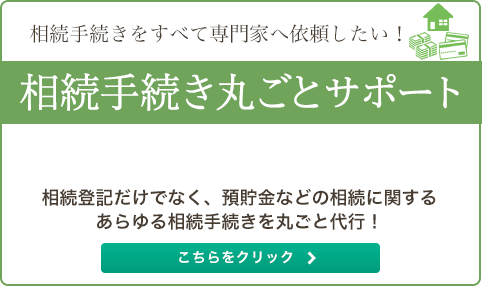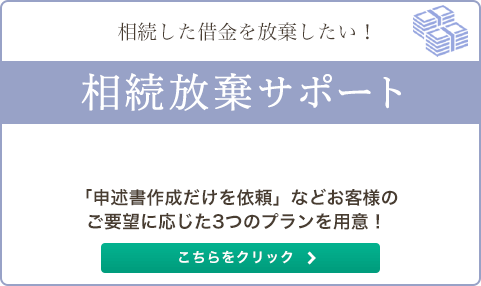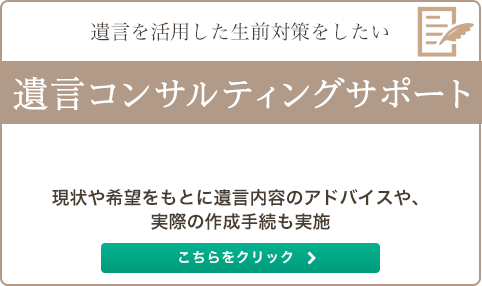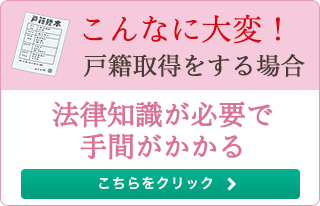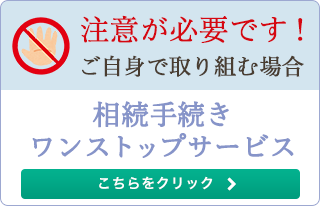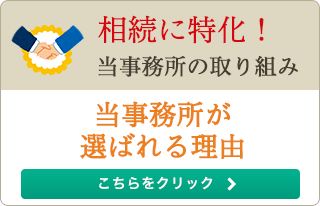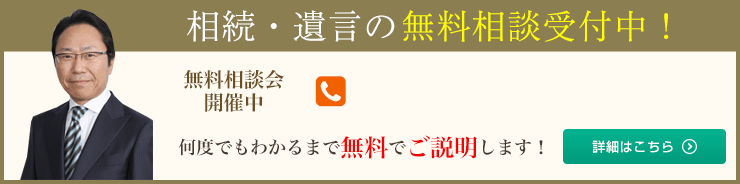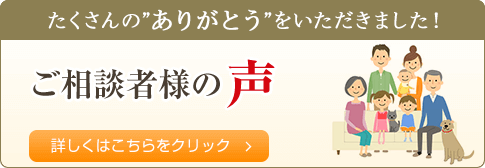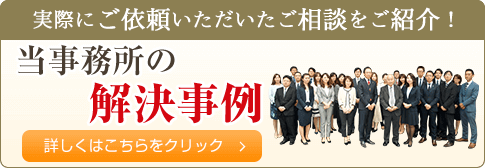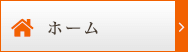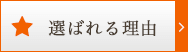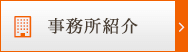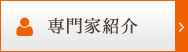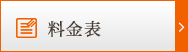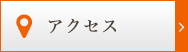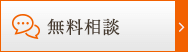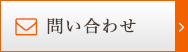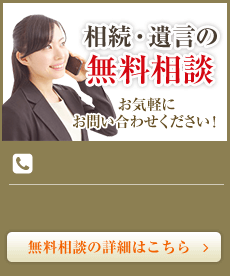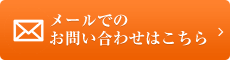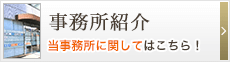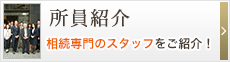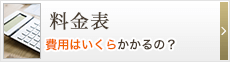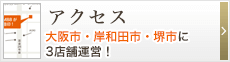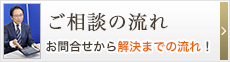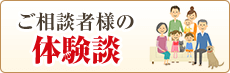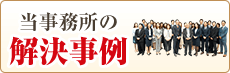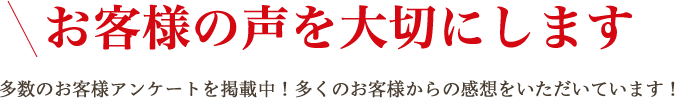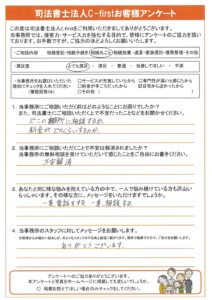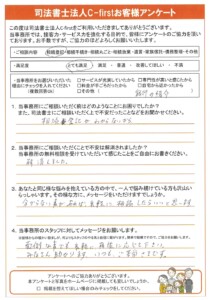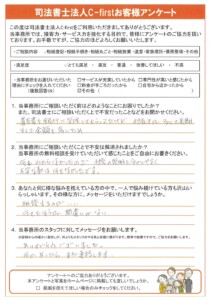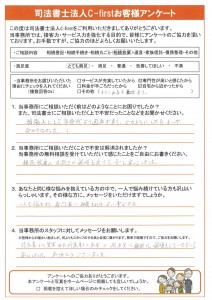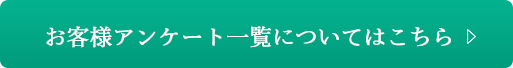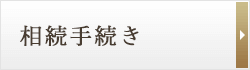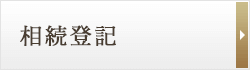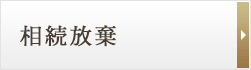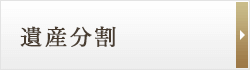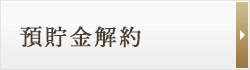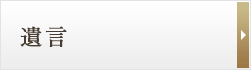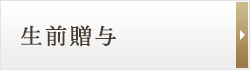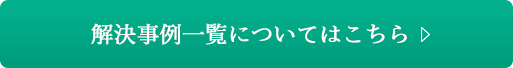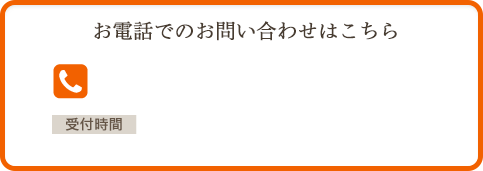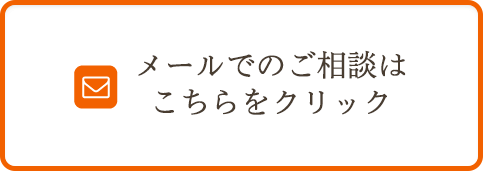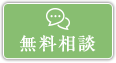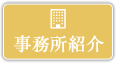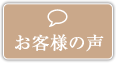【認知症の相続人がいる】相続手続きの進め方と成年後見人制度について解説
認知症の相続人を無視して相続手続きできる?

認知症等の方が相続人になる場合、そのままでは相続手続きを行うことは出来ません。
それは、認知症等の方が正しい判断能力(意思能力)を持たない状態では、遺産分割においても正しい判断が出来ないためです。
そうした相続人の方がいる状況で作成した遺産分割協議書は無効となり、法律的には効果を発揮することが出来ませんので、きちんと法律に則った手続きを進めることが必要となります。
また、そうした状況の方に強引に書類の判子を押させてしまっても、当然無効です。
認知症の相続人がいる場合は「成年後見人制度」の利用が可能
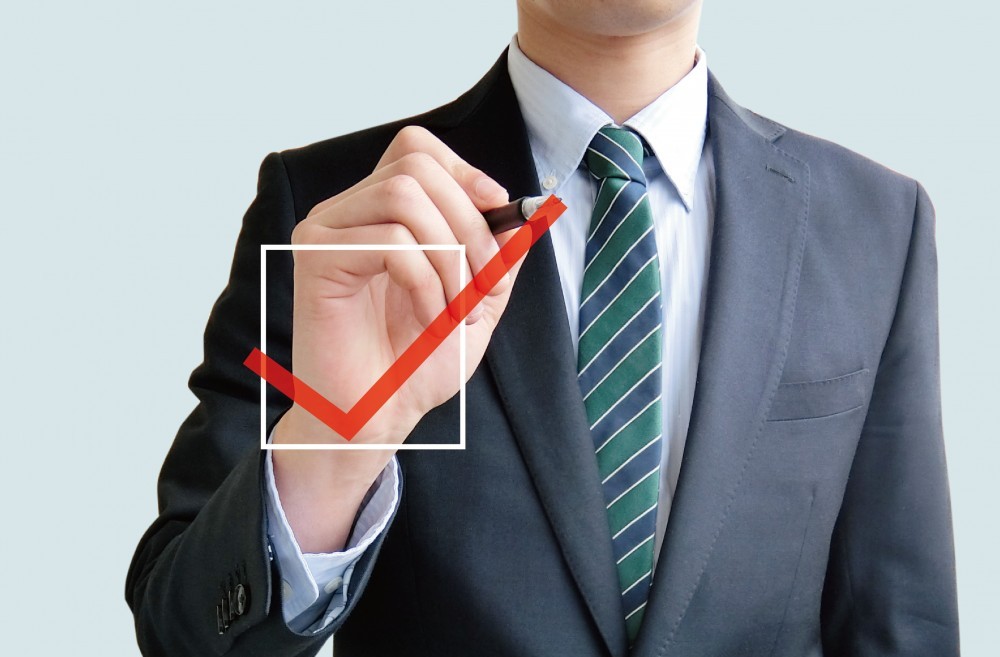
相続手続きを行うためには、相続人全員が遺産分割に同意していることが前提となりますので、相続人としての意思表示が出来ない方がいる場合、手続きを進めることが出来ません。
こうした場合には、そうした相続人に代わって遺産分割協議に参加する代理人が必要になります。
その代理人を成年後見人といいます。
このように、認知症の方が相続人にいる場合の相続手続を進めるにあたっては、まず家庭裁判所に成年後見開始申立てを行い、成年後見人が無事に選任されてから、成年後見人を含めた相続人全員で遺産分割協議を行う流れとなります。
このうえで、必要書類に署名捺印して相続手続きを進めて、財産の名義変更などができるようになります。
※ この場合、認知症等の方の程度によっては、成年後見人、保佐人、補助人など、種類が変わることがあります。
成年後見人の選任は、家庭裁判所で行われますので、家庭裁判所に対して成年後見開始の申立てを行う必要がありますが、成年後見人が選任されるには、認知症の方の鑑定等が必要な場合もあり、選任されるまで、一般的には2~3ヶ月は時間がかかります。
相続手続きがスムーズに進めるためには、早めに専門家にご相談いただく必要があります。
成年後見人の申立をせずに相続手続きを進める方法
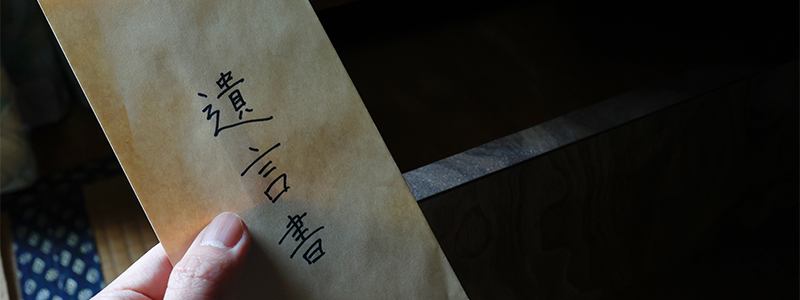
認知症の相続人がいた場合、必ずしも成年後見人を選出しないといけないわけではありません。
また、成年後見人制度の利用には手間や時間がかかることもあります。
成年後見人を立てない場合は、
・遺言書の内容に従って遺産分割
・法定相続分に従って遺産分割
という方法を選択することも可能です
被相続人の遺言書に従って遺産分割
被相続人の正式な遺言書がある場合、遺言書に従って相続するのであれば遺産分割協議は必要ありません。
遺言による相続は、意思能力がない認知症の相続人であっても、代理人を立てることなく遺産を受け取り可能です。
遺産分割協議をせずとも不動産や預貯金について、凍結を解除し相続手続きをすることができます。
法定相続分に従って遺産分割
法定相続分どおりに相続する場合も、遺産分割協議は必要ありません。
相続人が行う法律行為ではないので、法定相続分に従って遺産分割をするのであれば、認知症の相続人も遺産を受け取れます。
成年後見人を立てない場合の注意点
遺産の中に不動産がある場合は注意が必要になります。
法定相続分に従って遺産分割を行う場合、相続人全員の共有名義によって相続登記をしなければりません。
実は、相続した不動産を売却する際には、認知症の相続人について代理人を立てる必要があります。
そのため、やっぱり最初から代理人を立てて、遺産分割をしておけばよかったと後悔されるケースが多いです。
当事務所では、成年後見人の申立をサポートすることも可能です。解決事例も多数ございます。
成年後見制度を使い認知症発症後にマンションの売却が出来たケース>>
家族信託の活用もおすすめ

認知症対策には「家族信託」も有効です。
家族信託とは、財産を信頼のできる家族に託し、自分や家族のために管理してもらうという財産の管理・処分の方法です。
判断能力のある間に、あらかじめ家族に財産を託しておきます。
万が一本人が判断できなくなったときでも、信頼できる家族に財産を管理してもらうことができます。
例えば、介護費用の不足が心配される場合、あらかじめ実家をお子様に託しておきます。そうすると、将来の施設入居時や資金不足になりそうなときに、託されたお子様が実家を売却して費用を工面することができるようになります。
家族信託によって承継先を定めておくことで、同様に遺産分割協議を回避することも可能なのです。
相続の無料相談実施中!
.jpg)
相続手続きや遺言書作成、成年後見など相続に関わるご相談は当事務所にお任せ下さい。
当事務所の司法書士が親切丁寧にご相談に対応させていただきますので、まずは無料相談をご利用ください。
予約受付専用ダイヤルは0120-079-077になります。お気軽にご相談ください。
相続手続き丸ごとサポート(遺産整理業務)の料金
相続人様の窓口として、相続の煩雑な手続きをすべて一括で丸ごと代行するサービスです。
相続人調査(戸籍収集)や遺産分割協議書の作成、「預金」「不動産」「株式」など、あらゆる相続手続きをまとめて代行致します。
遠方にお住まいの方や相続関係が複雑な方にオススメです。
サポート料金A:相続人間で話し合い可能な場合
サポート料金B:相続人間で話し合いできない場合
| 相続財産の価額 | サポート料金A | サポート料金B |
|---|---|---|
| 200万円以下 | 165,000円 | 330,000円 |
| 200万円超~500万円以下 | 220,000円 | 385,000円 |
| 500万円超~1,000万円以下 | 275,000円 | 440,000円 |
| 1,000万円超~2,000万円以下 | 385,000円 | 550,000円 |
| 2,000万円超~3,000万円以下 | 495,000円 | 660,000円 |
| 3,000万円超~4,000万円以下 | 605,000円 | 770,000円 |
| 4,000万円超~5,000万円以下 | 715,000円 | 880,000円 |
| 5,000万円超~6,000万円以下 | 825,000円 | 990,000円 |
| 6,000万円超~7,000万円以下 | 935,000円 | 1,100,000円 |
| 7,000万円超~8,000万円以下 | 1,045,000円 | 1,210,000円 |
| 8,000万円超~9,000万円以下 | 1,155,000円 |
1,320,000円 |
| 9,000万円超~1億円以下 | 1,265,000円 | 1,430,000円 |
| 1億円超 | 相続財産額の1.43% | 相続財産額の1.65% |
※相続税の申告が必要な場合の税理士報酬・弁護士、土地家屋調査士など各種専門家を手配した場合等は別途報酬が発生します。
※手続内容により下記のとおり各種加算させていただきます。
・手続き先数(金融機関の数、不動産の管轄数)9件目以降5.5万円/件 (不動産筆数)6筆目以降2,200円/件
・相続人5名様以降5.5万円/名 ・数次相続、代襲相続発生の場合5.5万円/件 ・債務の弁済がある場合 3.3万円/件
・相続人が海外在住または外国籍の場合11万円/名(連絡先不明の場合手続不可) ・相続放棄をされる方がいる場合4.4万円~/名
※上記料金の他に下記のような実費が必要です。
①登録免許税(法務局に支払う名義変更に必要な税金です。) 不動産評価額×0.4% ②戸籍謄本、登記簿謄本等
この記事を担当した専門家

司法書士法人C-first
司法書士
江邉 慶子
- 保有資格
司法書士 相続アドバイザー 2級FP技能士 行政書士 宅建士
- 専門分野
相続 遺言 生前対策 家族信託
- 経歴
大学卒業後、不動産会社に勤務。自身の祖父の相続経験から「相続争いになる人を減らしたい」という想いがあり司法書士試験にチャレンジし、合格。平成27年7月から「司法書士法人C-first」に入所。入所時から相続を担当し、相談件数400件以上。セミナー講師も務め、生前対策の大切さを伝える。