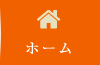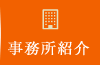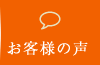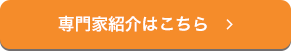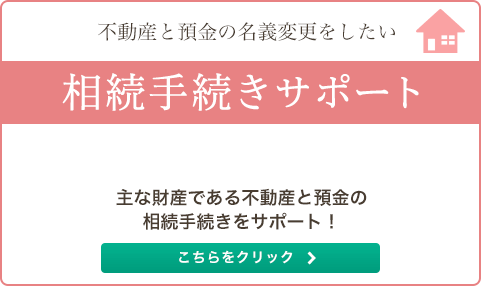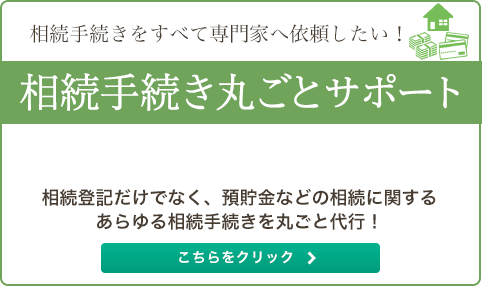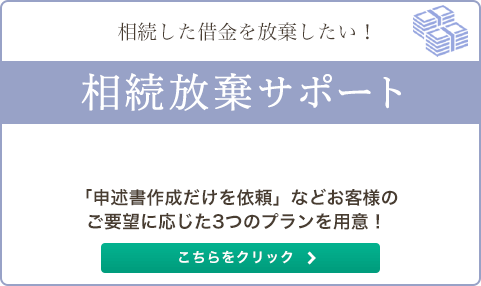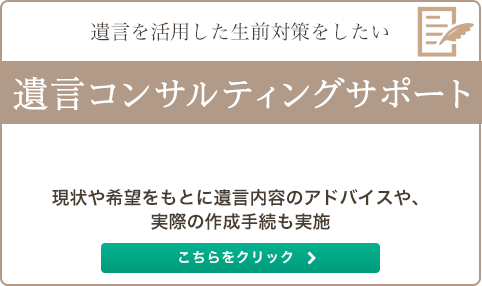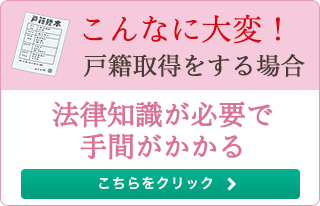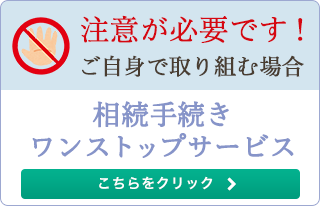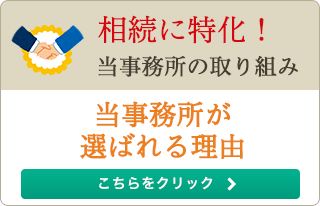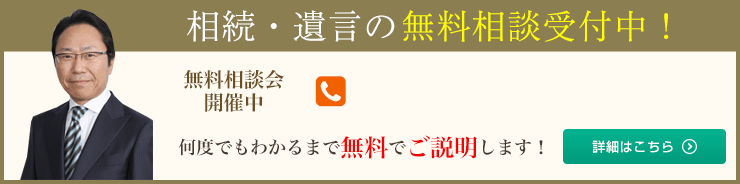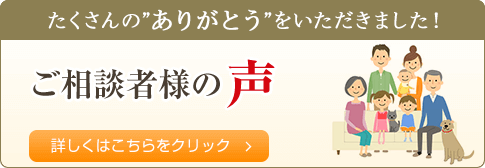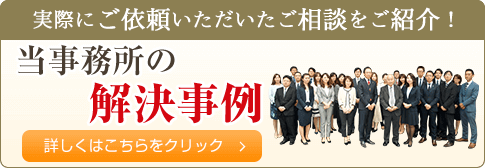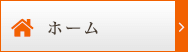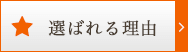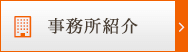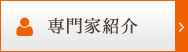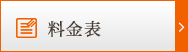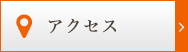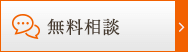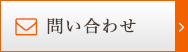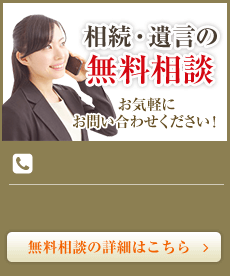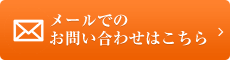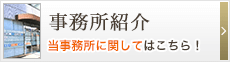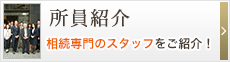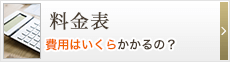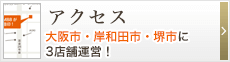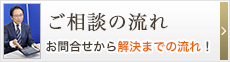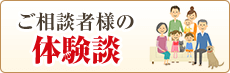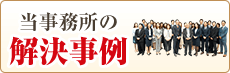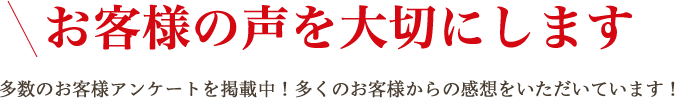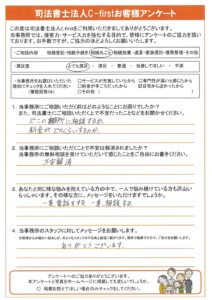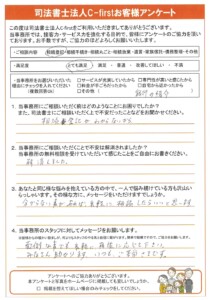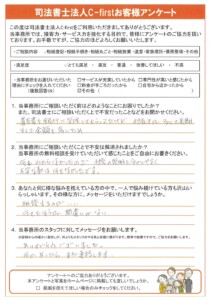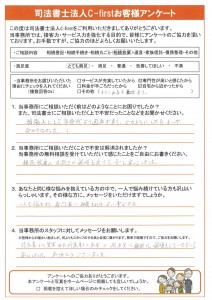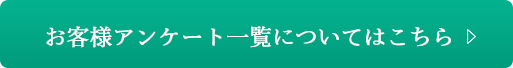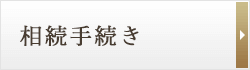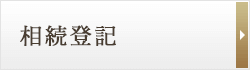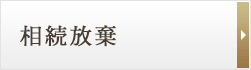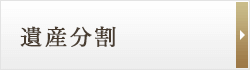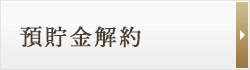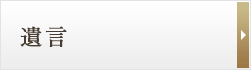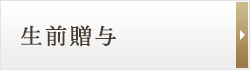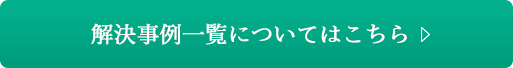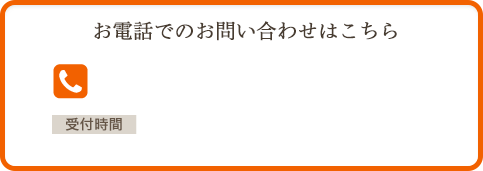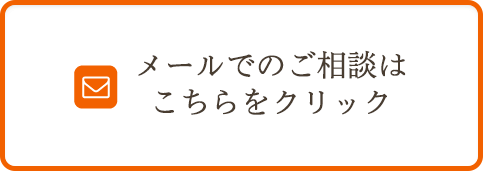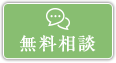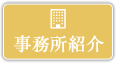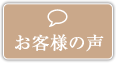公正証書遺言と秘密証書遺言の違いとは??どちらがオススメ?
大阪事務所の司法書士 北村維新(きたむら・いしん)です。今回は秘密証書遺言と公正証書遺言について比較をしつつ解説してまいります。
遺言は、自身の死後に財産をどのように分配するかを明確にするための重要な手段です。家は長女に相続させたい、預金は長男に相続させたい、一部の預金はお世話になった団体に寄付したいなど・・・全員が同じ内容ではなく十人十色の想いを込めて遺言を書かれます。
遺言と言えば、自身で作成する自筆証書遺言を考えられる方もいらっしゃいますが、その効力や形式面での不備がないかなど、自身の意思を正確に反映・実現できるか不安に思われる方もいます。
そのような方には弊所では遺言案の検討を行いつつ、公証役場にて公正証書遺言の作成をお勧めしているのですが、実は公証役場では公正証書遺言以外にも秘密証書遺言といった形式の遺言の作成もすることができます。
以下では、公正証書遺言と秘密証書遺言、2つの特徴を比較いたします。
1.作成手続きの違い
公正証書遺言は、公証役場にて公証人の面前で作成されます。遺言者は口頭でその内容を述べ、公証人がこれを文書化し、証人2名とともに署名押印することで成立します。元裁判官・検察官である公証人が関与するため、内容の不備や形式的な不適合が起こる可能性が低く、安全性が高いといえます。
一方、秘密証書遺言は遺言者自身が手書きまたはワープロ等で作成した遺言書(ただし、自筆で署名と押印は必要)を封印し、それを公証人と証人2名の前で提出・封印確認する形式です。誰にも内容を知られたくないからとご自身のみで作成された場合、内容を公証人が確認しないため、形式や記載内容に不備があっても気付かれない可能性があります。
2.遺言の安全性と確実性
公正証書遺言は、公証役場に原本が保管されるため、紛失や改ざんの恐れがありません。また、死後の家庭裁判所による「検認」手続きも不要で、速やかに内容を実現できます。
これに対して秘密証書遺言は、原本を遺言者自身または第三者が保管するため、紛失や隠匿、改ざんのリスクがあります。また、死後には家庭裁判所での検認手続きが必要となり、相続の開始に時間がかかることもあります。
3.遺言内容の秘密保持
秘密証書遺言はその名の通り、遺言の内容を秘密にできる点が特徴ですが、公正証書遺言でも証人の選定次第では、内容の漏洩リスクを最小限に抑えることが可能です。むしろ、秘密を優先するあまり形式面での不備が発見されず、無効となるリスクを考慮すると、公正証書遺言の方が総合的な信頼性は高いといえます。
4.費用と手間
公正証書遺言には一定の費用(士業の報酬に加え公証人手数料など)がかかりますが、それにより遺言の有効性・安全性が保障されます。将来の相続人間のトラブル防止や、確実な遺言内容の実現を考えると、費用以上の価値があると考えます。
秘密証書遺言は公正証書遺言と比較すると費用が安価で済みますが、前述のとおり、無効となるリスクや執行にかかる手間・時間を考慮すると、結果的に大きな負担や不安要素が残る可能性があります。
まとめ
公正証書遺言は、法的な安全性、内容の確実な実現、紛失や改ざん防止など、多くの面で優れており、特に遺言の内容を確実に実現したいと考える方にとっては最適な選択です。一方、秘密証書遺言は一見手軽に思えるものの、形式面でのリスクや執行時の課題が大きいため、安心・確実な遺言作成を目指すのであれば、公正証書遺言を選ぶことをオススメいたします。
司法書士法人C-firstでは相続開始後の相談だけではなく、生前対策として遺言の作成方法や税理士事務所と提携して、相続税を抑えるための提案を行っております。もし遺言の作成方法で悩んだときはお気軽にお問い合わせください。
この記事を担当した専門家

司法書士法人C-first
司法書士
江邉 慶子
- 保有資格
司法書士 相続アドバイザー 2級FP技能士 行政書士 宅建士
- 専門分野
相続 遺言 生前対策 家族信託
- 経歴
大学卒業後、不動産会社に勤務。自身の祖父の相続経験から「相続争いになる人を減らしたい」という想いがあり司法書士試験にチャレンジし、合格。平成27年7月から「司法書士法人C-first」に入所。入所時から相続を担当し、相談件数400件以上。セミナー講師も務め、生前対策の大切さを伝える。