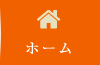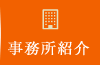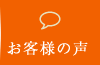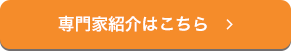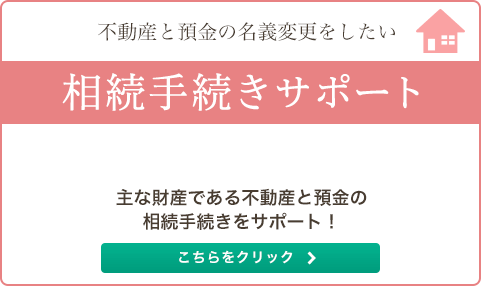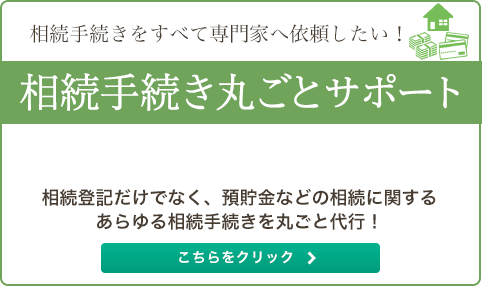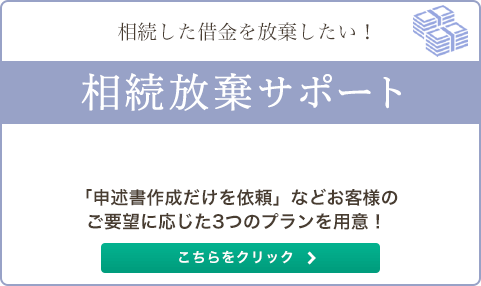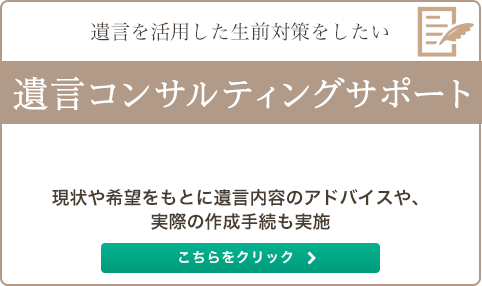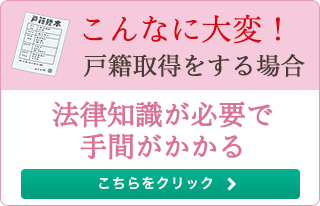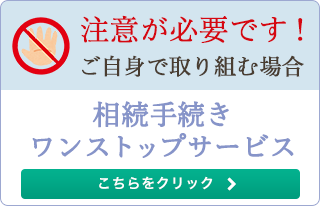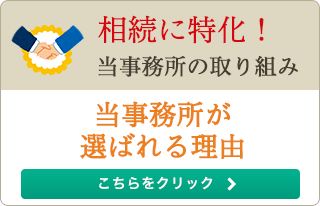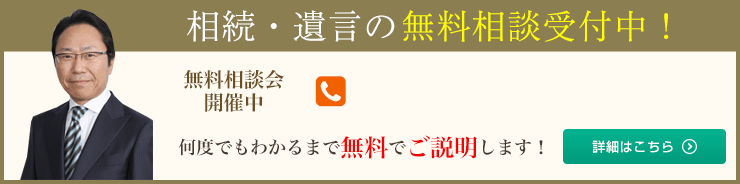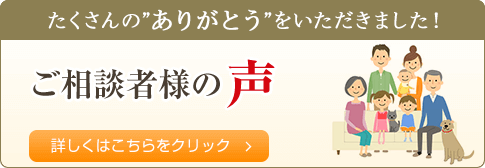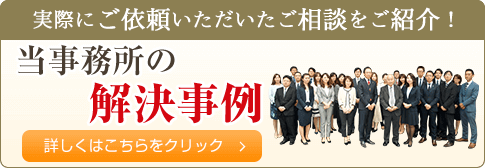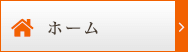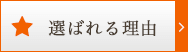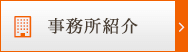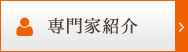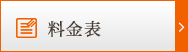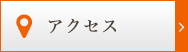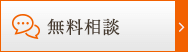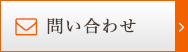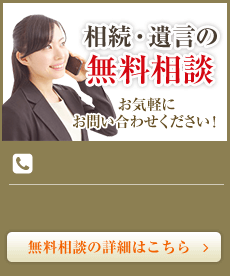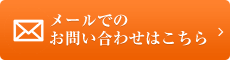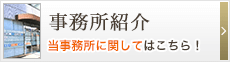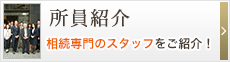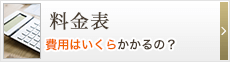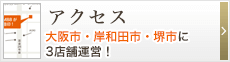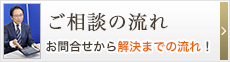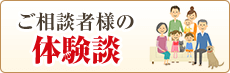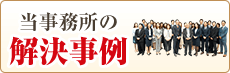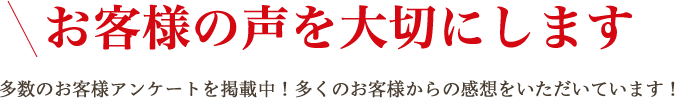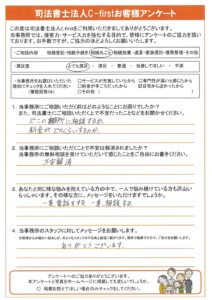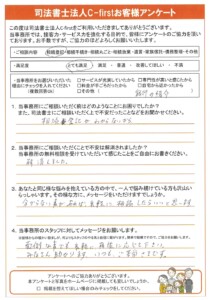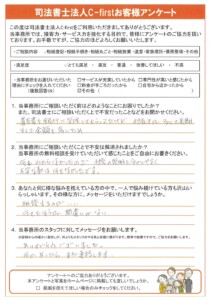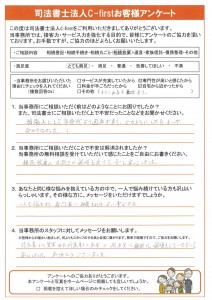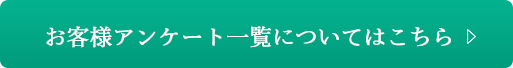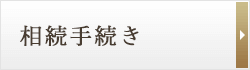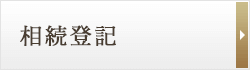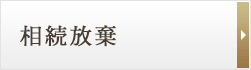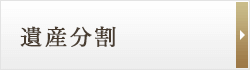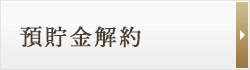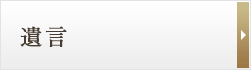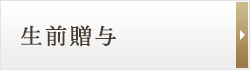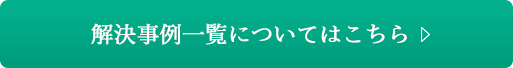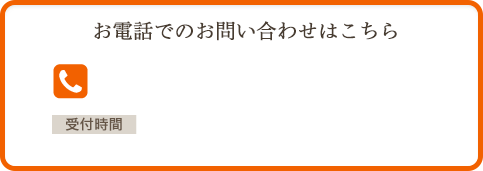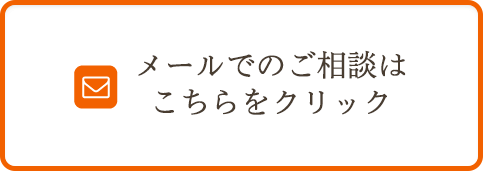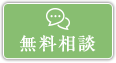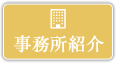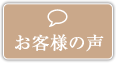亡き父の不動産!母と子どちらが相続するべき?
父が亡くなったら、父の持つ不動産を母と子のどちらが相続するのが最適なのでしょうか?
- • 父と同居していた母が相続するのがいいのか
• それとも子(あなた)が相続し、母に住んでもらうのか
• あるいは、不動産を共有するのか
こうした選択肢が浮かぶかもしれません。
そこで本記事では、父が亡くなったら不動産を誰に相続させるのが最適なのか、そのメリットとデメリットをわかりやすく解説します。慌てずに手続きを進めるためのヒントになるはずです。ご家族の思い出が詰まった大切な実家を守るために、一緒に確認していきましょう。

-
相続で実家の名義変更が必要な理由
相続は「放置できない」
「誰の名義になっても住む人は変わらないのだから名義変更は後回しで大丈夫かな?」と思いがちですが、2024年4月から相続登記が義務化され、怠ると過料が科される可能性もあります。
昔は放置することも選択肢の1つでしたが、今は理由なく相続登記を行わずに放置することはできなくなりました。
-
遺言がある場合とない場合
相続のときにまず確認したいのが、お父様が遺言を残されているかどうかです。
- • 遺言がない場合: 相続人全員が集まり、どのように遺産を分けるかを話し合って決める必要があります。
• 遺言がある場合: 原則として、その遺言書に書かれた内容に沿って相続を進めます。ただし、相続人全員が「別の分け方をしたい」と合意できれば、遺言とは異なる方法を取ることも可能です。
どちらにしても、みなさんでしっかり話し合うことが大切です。
-
実家の名義を「お母様」にする場合
メリット
-
お母様が安心して住み続けられる
子の名義にすると所有者である子が家の売却などを決めると、母は子から退去を迫られる可能性があります。母の名義であればこういった不安がありません。(配偶者居住権については後述)

-
相続税の優遇措置を受けられる可能性がある
配偶者には相続税の配偶者控除や小規模宅地等の特例が使えるケースが多いです。これによって相続税を大きく減らせることもあります。
-
配偶者の税額軽減(配偶者控除)
法律上の夫婦が相続や遺贈で財産を受け取る場合、1億6千万円または配偶者の法定相続分相当額のうち大きい方まで、相続税がかからなくなる制度です。
ただし、相続税の申告期限内に遺産分割が完了していることなど、いくつか条件があります。
この控除を利用すれば、残された配偶者の相続税負担を大きく減らすことができます。 -
小規模宅地等の特例
亡くなった方が住んでいた土地(または事業用の土地)を相続する際に、その土地の評価額を80%も減額できる特別なルールです。
-
-
- ・居住用宅地の場合は、最大330㎡までが対象。
- ・配偶者が相続する場合は、相続後に住み続けなくても80%減額が適用される。
-
この特例を使うことで、相続税の課税対象額が大幅に減り、相続税を安く抑えられます。
-
-
-
ご家族みんなの納得を得やすい
お母様が住み続ける前提であれば、ほかのご兄弟も「まずはお母さんが落ち着いて暮らせるように」と協力しやすいでしょう。
上記で解説した「配偶者の税額軽減」と「小規模宅地等の特例」の両方が適用される場合、一次相続(父親が亡くなった際の相続)においては、配偶者(母親)の相続税負担は非常に軽くなる、あるいは相続税が発生しないことが多いと言えます。特に、居住用の不動産が主な相続財産である場合、これらの特例を最大限に活用することで、母親は安心して住み続けることができ、かつ相続税の心配を軽減できる可能性があります。
デメリット
-
二次相続の手間と費用
いずれお母様が亡くなったとき、実家の不動産をもう一度相続する(=二次相続)手続きが必要になります。
-
- ①手続きの重複: 相続登記(不動産の名義変更)には戸籍謄本や住民票の除票など、多くの書類を集める必要があります。お母様名義に替えた後、二次相続でもまた同じような手続きを繰り返さなければならないため、手間が2回分かかります。
- ②費用が増える: 相続登記には、登録免許税・書類取得費用・司法書士への報酬などが発生します。
- ・お母様への相続登記
- ・お母様が亡くなった際の子供への相続登記
2回分の費用が必要になるので、経済的負担が増える可能性があります。
-

-
お母様の判断能力が低下した場合(認知症など)
もしお母様が認知症などで判断能力が低下すると、実家の売却やリフォームをしたくても簡単にはできなくなるかもしれません。
-
- ①法律行為の制限: 認知症が進むと、不動産の売買契約など、難しい判断を伴う手続きが自分だけではできなくなる可能性があります。
- ②成年後見制度の利用: 売却やリフォームが必要なときに、お母様の代わりに契約を結ぶ人(後見人)を選ぶため、家庭裁判所への申立てや手続きが必要になります。
- ・手続きが複雑
- ・時間がかかる
- ・後見人への報酬が発生することも
- ③売却の遅れ: 後見人選任などに時間がかかり、すぐに不動産を現金化できないこともあります。
-
-
将来的な兄弟間の意見の食い違い
お母様が亡くなったあと(=二次相続)に、実家をどうするかで子供たちの意見が衝突する可能性があります。
-
- 遺産分割協議の難航: 不動産を「誰が相続するのか」「売却して分けるのか」など、相続人全員で話し合いが必要です。これがまとまらないと相続手続きが進まず、トラブルに発展しかねません。
- 家族関係の悪化: 同居していた子供と別居の子供など、立場が違う兄弟姉妹同士で意見の食い違いが起こり、関係がギクシャクしてしまうこともあります。
-
-
実家の名義を「子ども」にする場合
メリット
-
二次相続の手続きに自宅が含まれない
お母様が亡くなられても、すでに子どもの名義になっていれば、再度の相続登記は不要です。 -
資産活用の自由度が高い
将来的にお子さんが実家をどう活用するか(売却・リフォーム・賃貸など)、自分の判断で進めやすい点は大きいです。 -
今のうちに特定のお子さんに確実に引き継がせられる
将来「どの子が実家を受け継ぐか」でもめそうな場合、早めにひとりの名義にしておくのも一つの方法です。
デメリット
-
お母様の精神的な不安
所有者である子から退去を求められる不安が残ります。そこで利用できるのが配偶者居住権です。
配偶者居住権は、残された配偶者が家に住み続けられるよう、家の所有権とは別に「住む権利」を設定する仕組みです。
この制度を利用すれば配偶者が住む権利を得て安心して住み続けられる一方で、下記のデメリットもあります。-
- 登記手続きが必要
- 不動産価値を下落させる要因になる
- 途中で配偶者居住権を放棄した場合は贈与税が課税されるリスクがある
-
-
相続税の軽減措置が使えない場合がある
配偶者であれば適用される控除や特例が、子どもには適用されず、相続税が高くなるケースも考えられます。
いったん名義変更すると再変更することが難しく、あとで別の子どもやお母様に名義を移そうとしても、贈与税がかかる可能性があります。
不動産を共有するのはオススメできない
不動産を共有名義にすると、売却や賃貸、管理などのあらゆる場面で共有者全員の同意が必要になり、手続きが複雑化しやすいうえ、相続や認知症リスクによって共有者が増えたり意思決定が難しくなったりする可能性があります。結果的に不動産の活用や売却ができずに負担だけがかかる「負動産」化し、将来的な紛争や手続きの煩雑さを子や孫の世代にも引き継いでしまうおそれがあるため、専門家は共有名義を推奨しないことが多いです。
まとめ
母親に不動産を相続させると、最大のメリットは税制面の優遇と、母の安心感です。
「配偶者の税額軽減」により、最低でも1.6億円までは相続税がかからず、一次相続の税負担を大幅に減らせます。ただし、母親が亡くなった後の二次相続では同じ軽減措置を使えず、相続税が増える可能性がある点に注意が必要です。
一方、父親の不動産を子が直接相続すると、母親が亡くなる際(二次相続)には父の不動産の相続登記が必要ないため、トータルの相続費用や手続きの手間を軽くできる可能性が高いです。さらに、母親が認知症になっても、子が名義人であれば売却などの手続きをスムーズに行える点や、相続登記が一度で済むため費用や手間を抑えられる点もメリットとなります。
この記事を担当した専門家

司法書士法人C-first
代表社員
山内 浩
- 保有資格
代表社員司法書士 家族信託専門士
- 専門分野
家族信託 相続 遺言 生前対策
- 経歴
司法書士法人C-firstの代表を務める。平成6年4月に貝塚市にて開業、平成25年4月には合併を経て事務所名をC-firstに改名。高齢者の生前対策について新しい財産管理承継ツールである家族信託などを活用して、高齢者の生前対策に最適なプランを提供する。